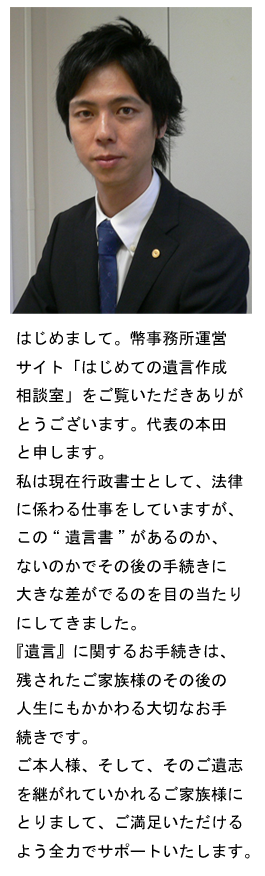遺言書の種類
遺言書作成の方式
『法律で定める方式以外の遺言書の作成は無効です』
民法によれば、遺言書は、この法律(民法)に定める方式に従わなければ、これをすることができない。
と規定されています。
つまり、民法の規定に従わない遺言書の作成は有効とは認められないということです。
遺言書には、3通りの方式が民法で定められています。
①自筆証書遺言
②秘密証書遺言
③公正証書遺言
上記のなかで、一番強力な効果をもたらす遺言書は③の公正証書遺言です。
▲ UP
自筆証書遺言
本人が、本文の全文・日付・氏名を自筆で書いた書面に捺印したものです。
用紙は何でも構いませんが、ワープロ文字や代筆は認められず、必ず自分で書くことが必要となります。
このように、誰にも依頼せず自分自身で書くものですから特に費用はかかりませんし、思い立ったらすぐに書くことができるので他の方式と違い手間がかかりません。
しかし、パソコンやワープロを使用することはできませんし、全て手書きとなりますので、その内容に不備があると遺言書の全てが無効とされてしまう可能性もあります。
問題点としては、法律的に間違いのない文章を作成することはなかなか困難なことですし、保管上の問題もあります。
それに、遺言執行の際には家庭裁判所で「検認手続」をしなければなりません。
よく筆跡鑑定などで真実性が争われているのが、この遺言書です。
▲ UP
公正証書遺言
公正証書遺言は、公証役場において公証人といわれる方に遺言書を作成してもらい、その内容を本人と、本人以外の第三者である証人2人を含めて署名捺印して証書を公証役場に保管してもらう方式のものです。
遺言者が公証役場へいけないときなどは、公証人が出張にて出向いてもくれます。
(もちろん、別途に費用が必要ですが。)
上記に、遺言書の方式で一番強力な効果と書きましたが、
どの方式も遺言書の内容自体の効果が変わるわけではなく、
のちの相続手続きのときに、公正証書遺言が間違いなく遺言者本人の意思で作られた遺言書であることが確認できることから、遺言者死亡後の手続きも裁判所などを通すこともなく極めて簡単なものとなり、実効性が強い遺言書となるという意味です。
この方式の遺言書が一番おすすめできるものです。
参考になるビデオを紹介しておきます。
▲ UP
公正証書遺言の利点
1.原本が公証役場に保管されるため、紛失や偽変造の恐れがない。
2.家庭裁判所における検認手続が不要。
3.法律の専門家である公証人が遺言書を作成しますので、内容に間違いがない。
ただしこのような点もあります!
- 事前に原案を作成・準備しておく必要がある。
- 原案の段階で、具体的な配分なども決めておかなくてはならない。
(行政書士などの専門家に依頼して作成することもできます) - 証人が立ち会いますので秘密の保持が困難。
行政書士が証人となった場合には、法律で守秘義務が課せられていますので安心です。
(知人に証人を頼むことは避けた方が賢明です)
- ある程度の費用がかかる。
▲ UP
公正証書にかかる手数料
公正証書遺言作成には、公証役場への手数料がかかります。
公正証書作成の手数料等は、政府が決めた公証人手数料令により、法律行為の目的価格に従って、次のように定められています。
| 目的の価額 | 手 数 料 |
| 100万円まで | 5,000円 |
| 200万円まで | 7,000円 |
| 500万円まで | 11,000円 |
| 1,000万円まで | 17,000円 |
| 3,000万円まで | 23,000円 |
| 5,000万円まで | 29,000円 |
| 1億円まで | 43,000円 |
| 3億円まで、5,000万円ごとに13,000円加算 | |
| 10億円まで、5,000万円ごとに11,000円加算 | |
| 10億円超は、5,000万円ごとに 8,000円加算 | |
- 遺言の場合は、相続人、受遺者毎に価額を算定して合算。不動産は、固定資産評価額を基準に評価
- 相続、遺贈額合計が1億円に満たないときは、11,000円を加算
- 紙代として、数千円を加算
- 以上のほか、公証人が病院等に出張して公正証書を作成するときは、目的価額による手数料が通常の1.5倍になるほか、規定の日当(半日1万円)、旅費交通費(実費)を負担することになります。
具体例
1. 相続人が1人で相続財産が5,000万円の場合の手数料
29,000円+11,000円=40,000円
2. 相続人が3人で相続財産が1人2,000万円の場合の手数料
23,000円×3+11,000円=80,000円
3. 相続人が3人で相続財産が
7,000万円、5,000万円、3,000万円の場合の手数料
43,000円+29,000円+23,000円=95,000円
▲ UP
秘密証書遺言
この遺言書は、公正証書遺言と同じく公証役場を使う制度です。
ただし、公正証書遺言との違いは、遺言書そのものは遺言者で作成し、公証人は全く遺言書の内容は関与しません。
そして、公証役場備え付けの封筒に、持ち込んだ遺言書を封入してそれに封印と署名をするだけの方式です。
ですので、遺言書が存在することを公証人が証明してくれて、第三者の証人2名が必要ですが、その内容については遺言者本人しか知らないことになります。
この場合は自筆証書遺言と違い、パソコンやワープロを使用しても構いません。。
やはりこの方式の遺言書も、内容の正確さの問題や検認手続の問題があります。
▲ UP
各遺言書の特徴とメリット・デメリット
| 自筆証書遺言 | 公正証書遺言 | 秘密証書遺言 | ||
| 作成方法 | 本人が遺言の全文と日付・ 氏名を書いて、押印(認印でもよい)する。( ワープロ・テープ不可。 遺言書が何通もあるときは、日付の最も新しいものが優先される。 内容を加除訂正する場合は、変更場所にその指示 を付記して署名・押印する。) | 本人が口述し、公証人が筆記する。 ~必要書類~ ・印鑑証明書 ・身元確認の資料 ・相続人等の戸籍謄本、登記簿謄本 |
本人が遺言書に署名捺印後、遺言書を封じ、遺言書に使用したものと同じ印で封印する事。 公証人の前で本人が住所、氏名を記す。 公証人が日付と本人が述べた内容を書く。(ワープロ・代筆可) | |
| 場所 | 自由 | 公証人役場 | 公証人役場 | |
| 証人 | 不要 | 証人2人以上 | 公証人1人、証人2人 | |
| 署名捺印 | 本人 | 本人、公証人、証人 | 本人、公証人、証人 | |
| 家庭裁判所の検認 | 必要 | 不要 | 必要 | |
| メリット・デメリットについて | ||||
| メリット | 証人の必要がない。 遺言を秘密にできる。 費用がかからない。 |
証拠能力が高い。 偽造の危険がない。 検認手続きが不要。 |
遺言の存在が明確。 遺言の内容は秘密。 偽造の危険がない。 |
|
| デメリット | 紛失、偽造の危険性がある。 方式不備による無効の可能性が生じる事がある。 検認手続きが必要。 |
作成手続が煩雑になりやすい。 遺言を秘密にできない。 費用がかかる。 証人2人以上の立会が必要になる。 |
作成手続が煩雑になりやすい。 費用がかかる。 検認手続きが必要。 |
|
▲ UP
遺言書作成の5つのポイント
1. 記載は正確にすること
相続人の名前、生年月日、誰になにを相続させるかを具体的に書くことが大切です。
2. 漏れをなくすこと
預貯金や株券、貴金属類、土地家屋など、相続財産を全て書き出すことが必要です。
漏れがあるとそれを誰が相続するかということで新たな火種になります。
それでは、遺言書を書く意味もなくなってしまいます。
3. 遺言書は、公正証書で作ること
遺言書には3種類ありますが、できれば公正証書遺言をお勧めします。
公正証書は、公証人に支払う手数料は多少かかりますが、改ざんされたり、紛失したりの心配はありません。
作った遺言書の原本は、公証人役場に1部保管されます。
4. 遺留分を考慮する
相続人には、これだけはもらえるという最低限の相続分があります。
この人にはあげたくないといってもその分を侵してしまうと、侵された相続人が、
家庭裁判所に遺留分減殺請求をしたら、侵害された部分を返す必要が出てきます。
それを侵さない程度に相続分を考えることが必要です。
5. 遺言執行者の指定
被相続人が無くなったときに遺言の内容を実現するために選任されるのが、遺言執行者です。
遺言書を書くときに指定しておくと、相続人が遺言書の内容どおりスムーズに実行することができます。