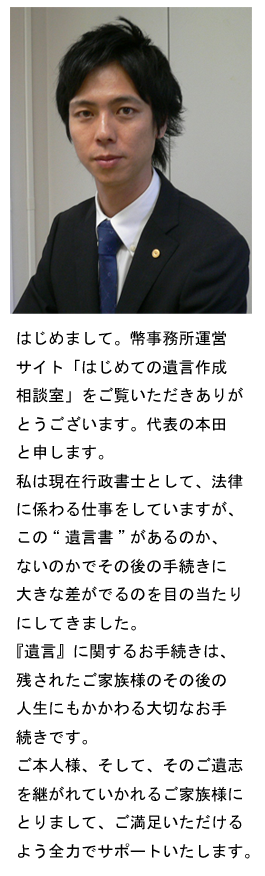遺言書の基礎知識・初級編
遺言書とは
遺言書とは、死期がせまっている人がすることだと思っていませんか?
また、「自分には関係ない」なんて思っていませんか?
遺言と聞くとだいたいは、あまりよくないイメージを持ちますよね。
おそらく、それは死を連想させることは縁起が良くないことだと
どこかで決めつけているからではないでしょうか?
では、同じく死を前提とした生命保険はどうでしょう。
ほとんどの方がしっかり入っていらっしゃいます。
この違いはいったいどこからくるのでしょう。
私は現在行政書士として、法律に係る仕事をしていますが、
この生命保険ではない遺言書という文書があるのか、ないのかで
その方の残された家族が余計な争いごとに巻き込まれたり、
そうでなかったりということを、目の当たりにして知っています。
遺言の誤ったイメージには、
・お金持ちにかぎったことで、財産のない自分には関係ない
・ある程度、歳をとってから考えればいい
・遺言なんて残さなくてもなんとかなるだろう
・自分が死ぬ前に家族に言えば大丈夫だ
・仲がいいので、自分がいなくてもしっかり整理してくれるだろう
しかし、こうした遺言について、生前に真剣に考えていなかったために
残念な結果におちいっている親族が後を絶たちません。
その理由として、
遺言書がなかった場合のデメリットとしては以下のようにことがあげられます。
1.相続人全員の遺産分割協議書ができないと銀行口座さえ凍結される
2.遺産の分配をめぐり、争いがおこりやすい
3.未成年や行方不明、海外在住の相続人がいる場合は、
相続手続きが複雑で進まない
4.相続人全員の合意がないと相続手続きが進められない、など
上記のとおり、「遺産がたくさんある」、「遺産なんて無い」という、持っている持ってないの理由は全く意味をもたず、ただ単に相続手続きをスムーズにするためにも遺言書が必要であることがお解りでしょうか。
実は、遺言書は、ごく普通の人にとっても必要とされるものなのです。
家庭裁判所に持ちこまれる、相続問題の三分の二は、遺言書が書いてあれば、
解決したと言われているのが現状です。
遺産分割に関する調停・審判件数は年々増えていて、現在は誰もが知っている高齢化社会ですので、今後もこの伸びは増え続けると考えられます。
あなたがそのような裁判ごとに大事な家族を巻き込ませないためには、
しっかり遺言書を遺すことでしか対処がないのです。
生きている間は、自分の意志で自由に財産を処分できますが、もし万が一のことがあった時に、残された家族達は故人の意思を確かめることは出来ません。
故人の意思を尊重したくとも、その意思を確認する術が無ければどうしようもないのです。
そのときに“遺言書”という、形になったものが残されていたとしたら、
家族達は故人の意思を確認することができ、その内容に沿った形での財産の配分が可能になります。
遺言書を作成することによって、残された家族達に無用の心配をかけることが避けられるのです。
生前に遺言書を作成しておくことは、決して“自分には全然関係のないこと”でも、
“縁起でもないこと”でもないのです。
残される家族のための思いやりとして、そして安心を贈るために、
遺言書を作成しておくことをおすすめします。
それ以上に、遺言を作成することは、本人(遺言者)の生きた証を残す行為でもあります。
つまり、遺言とは、自分が生涯をかけて築き、かつ守ってきた大切な財産を、
最も有効・有意義に活用してもらうために行う、遺言者の最終的な意思表示です。
作成されてみれば気がつくと思いますが、財産を把握したり、相続人を特定し、
また、分配を考え、こうしたことは、『自分を知る』ことになりますので、
最終的な自分の意志表示することは、生きている実感につながります。
ここで気をつけなければいけないのは、遺言の方式は法律で定められているという
点です。
なぜなら、それに違反する遺言は無効となってしまうからです。
遺言は死ぬ前であれば、いつでも本人の意志で自由に変更(撤回)することができます。
もちろん変更(撤回)するときも、法律上の方式を守らなければいけません。
遺言で定めることが出来る内容も法律で決まっていますので、
それ以外の事柄について定めても何の効力もありません。
▲ UP
なぜ必要なのか
遺言とは、「人の最終意思に、死後法的効果を認めて、その実現を保証する制度」です。
家庭裁判所に持ち込まれる相続争いの多くは、正式な遺言書がないためだといわれています。
長きにわたり一生懸命働いて築いた財産も遺言がないために、
残された肉親同士が遺産争いを繰り広げるようでは、天国にいるはずの本人もやりきれないでしょう。
子孫の幸福のためになるべき遺産が、骨肉の争いを引き起こし、不幸の原因になってはたまりません。
財産のある人は、生前に自分の財産の状況とその行方を定めた遺言を作成するべきです。
遺言は遺産をめぐるトラブルを防ぐ最善の方法であるとともに、
遺産を世のため、人のために生かす出発点でもあります。
また、残すのは借金だけだという場合でも、残された家族が法的な手続(相続放棄)により借金の返済義務を負わなくてすむよう、その内容を遺言というかたちで書き残しておきたいものです。
▲ UP
遺言書をつくるメリット
◆ 特定の人に遺産を相続させたい場合
「子どもがいないので妻に全財産を相続させたい」
夫が亡くなれば、妻が全財産を相続すると考えがちですが、そうとは限りません。
夫に親兄弟や甥姪がいれば、その人にも相続権があります。
遺言書をつくれば、妻に全財産を相続させることができます。
そして、妻が安心して老後を暮らせるようになります。
「二世帯住宅で一緒に暮らしている長男に土地を譲りたい」
二世帯住宅は、親の土地に、長男単独か、親と共同で家を建てる場合が通常です。
この場合、他の子どもとの間で土地の相続争いが生じ、結局家を売らなければならない場合もあります。
遺言書をつくれば、土地を同居の長男に相続させることができます。
「会社の経営を次男に引き継がせたい」
民法では、財産は平等に子どもに分配されるとありますから、
会社の株も子どもに分散され、経営の主導権をめぐって骨肉の争いになる場合もあります。
遺言書をつくれば、会社の経営を次男に継がせることができます。
「自分の面倒を看てくれる長女に財産を多く相続させたい」
子どもでも、老後の面倒を看てくれる子と看てくれない子がいます。
遺言書をつくれば、具体的な理由を書いて、
自分の面倒を看てくれる長女に財産の多くを相続させることができます。
(長女の方は、介護費用の領収書などをとっておく必要があります)
「妻の連れ子に財産を相続させたい」
実の子同様に育てられても、養子縁組をしていない再婚相手の連れ子は法律上の親子ではありません。
遺言書をつくれば、養子縁組をしないときでも、遺贈の形で財産をのこせます。
「独身だが身寄りがなく世話になった友人に財産を贈りたい」
遺言書がないと原則として財産は国庫に帰属します。
遺言書をつくれば、お世話になった恩人や、
身の周りの面倒を看てくれた人に感謝の気持ちをこめて財産を贈ることができます。
「財産の種類が多くて、相続がもめそうだ」
遺言者は財産を誰が相続するかを決めることができますが、種類が多いと、
財産を特定できなくなるおそれがあります。
遺言書をつくれば、土地建物は地番・家屋番号、銀行預金は口座番号、
株式はどの株式かの記載が必要なので、財産を特定することができます。
「家しか財産はないから遺言書なんて必要ない」
家以外に財産があれば家を売らなくても遺産分割できますが、家しかなければ、
家を売るかどうかでもめごとになるおそれがあります。
遺言書をつくれば、前もって自分の意志を家族に示すことができるので、
家族の間でのいらぬトラブルを避けることができます。
◆ この人には遺産を相続させたくないという場合
「日頃疎遠な兄弟に相続させたくない」
子どもも両親もいない場合、兄弟姉妹にも相続権が発生します。
日頃疎遠だった兄弟が遺産をアテにして急に接近してきたりすることがあります。
遺言書をつくれば、全財産を配偶者に相続させることができます。
「姉と妹がいるが、姉には遺産を相続させたくない」
配偶者も子どももいない場合、財産を姉と妹が2分の1ずつ相続します。
しかし、姉妹でもまったく疎遠な関係で均等に遺産を相続させたくない場合もあります。
遺言書をつくれば、姉と妹の間で感情的な対立が生じるような場合でも、
その理由を書いて、妹だけに遺産を相続させることができます。
◆ 遺産をこんなふうに使いたいという場合
「お墓や祖先の供養が心配だ」
死んでいく者にとって、遺族が墓を守り祖先を供養してくれるかどうかは心配事の一つです。
お墓は故人が生前に買えば相続税はかかりませんが、維持費は負担が必要です。
遺言書をつくれば、お墓を引き継ぐ人を生前に指定することができ、
お墓の維持費も相続財産で手当てしておくことができます。
「葬式や法要のやり方を決めておきたい」
自分が死んだらどんな葬儀が行われるのか。「親族だけで静かに」と願っていても、
実際は壮大な葬儀が相続人によって行われたりします。
遺言書をつくれば、遺言者の最後の意思が尊重されやすくなるので、
実行可能な範囲で、希望どおりの葬儀を行うことができます。
「かわいがっているペットの世話を頼みたい」
自分がいなくなった後のペットのことが心配な人も多いでしょうが、
法律上ペットは人ではなく物なので、相続させたり遺贈もできません。
遺言書をつくれば、ペットの世話をしてくれそうな人を探し、
その人に財産を贈ることを条件に、ペットの世話を頼むことができます。
▲ UP
遺言で出来ること
遺言で出来る事柄は法律で定められている一定の事項に限られます。
(1)狭義の相続に関する事項
①推定相続人の排除・取消し
②相続分の指定・指定の委託
③特別受益の持戻しの免除
④遺産分割の方法指定・指定の委託
⑤遺産分割の禁止
⑥共同相続人の担保責任の減免・加重
⑦遺贈の減殺の順序・割合の指定
(2)遺産の処分に関する事項
⑧遺贈
⑨財団法人設立のための寄付行為
⑩信託の設定
(3)身分上の事項
⑪認知
⑫未成年者の後見人の指定
⑬後見監督人の指定
(4)遺言執行に関する事項
⑭遺言執行者の指定・指定の委託
(5)学説で認められている事項
⑮祖先の祭祀主宰者の指定
⑯生命保険金受取人の指定・変更
遺言によって財産を与えることを「遺贈」といいます。
遺言書に書く場合、法定相続人には「相続させる」と書きますが、
遺言者の友人などに財産を与える場合には、この「遺贈」という言葉を
使います。
この場合、財産を受ける側の意思に関わりなく贈られます。
ですから、あげる、もらうという無償の契約である「贈与」とは法律上区別されています。
こういった法律の専門的な言葉を知っていないと、せっかくの遺言者の意志もまったく意味のないものとなってしまいます。
第三者である専門家に相談し、法律的に有効かどうかをチェックすることが
望ましいとかたちといえるでしょう。
遺言によって被相続人の意思を、なぜ明確に示す必要があるのかというと、
相続のトラブルの多くを未然に防ぐことができるからです。
▲ UP
遺言書で出来ないこと“遺留分”とは?
『遺言といえど、その効力には限界があります』
(1)「遺留分」とはどういうことか?
遺言で財産を受け取ることができなかった相続人には、相続財産の一定割合を受ける権利があります。
これを遺留分といいます。
相続人の生活を守るためにもうけられた制度で、民法では相続人に遺留分という権利を認めているのです。
遺留分は、遺言でも変えることができない、相続人が財産をもらうための最低限の割合です。
遺留分を持っているのは、配偶者、子供、親だけで、兄弟姉妹にはありません。
これを侵害している場合は、侵害を受けた相続人からの請求によって返さなければいけません。
(請求がなければ返す必要はありません。知らぬが仏ということもあるでしょう)。
たとえば、「愛人に全財産を相続させる」という内容の遺言を作っても、
「遺留分権利者」がその財産のうちそれぞれの遺留分に相当する財産を「減殺」する(とりもどす)ように求めれば、遺言のとおりになりません。
これを「遺留分減殺請求権」の行使といいます。
「遺留分権利者」とは 法定相続人のうち、兄弟姉妹以外の相続人で、遺留分を有する者をいいます。
相続人の権利は前もって放棄することはできませんが、遺留分については前もって放棄することができます。
被相続人が生前に遺言で定めた相続分を「指定相続分」といい、これは「法定相続分」に優先します。
財産の所有者はそれを自由に処分してかまわないからです。
しかしながら、財産処分の自由がどこまでも可能なわけではなく、
遺留分の制度によって、相続人には残さなければならない割合が定められていますので、
財産をどれくらい自由に処分できるかというと、遺留分の割合を差し引いた残りということになります。
(2)相続人に残す最低相続割合とは
遺言者の財産のうち、一定の相続人に残さなければならない割合を遺留分といいますが、
遺留分の権利者とその割合は次項のとおりです。
権利者は、法定相続人のうち子や孫などの直系卑属、父・母などの直系尊属と配偶者に限られており、兄弟姉妹には遺留分がありません。
例えば、遺言者が死亡、法定相続人が妻と子二人で「遺産の全てを長男に与える」
といった内容の遺言があった場合、妻ともう一人の子には遺産がないということになります。
つまり、妻ともう一人の子の遺留分を侵害している、というわけです。
(3)遺留分を侵害されたらどうするか
遺留分が侵害されていても、相続人が遺言どおりの配分を了承するならば、特に問題はありません。
遺留分を侵害された人は、遺留分に基づく減殺(げんさい)請求をする必要があります。
ただし、1年以内に主張しておかないと権利を失います。
減殺の請求権は、遺留分権利者が相続開始および、減殺すべき贈与または遺贈があったことを知ったときから、1年間行わないとき、または相続開始のときから10年を経過したときも時効によって消減します。
(減殺請求…不足分を取り戻すため請求すること)
▲ UP
遺留分の割合
1.直系尊属だけが相続人である場合は被相続人の財産の 1/3
2.その他の場合は被相続人の財産の 1/2
〔例〕妻と子2人が相続人の場合、
・妻の遺留分は4分の1(1/2 × 1/2)
・子1人の遺留分は8分の1(1/2 × 1/4)
| 法定相続人の例 | 遺留分の合計 | 相続人 | 法定相続分 | 遺留分 |
| 配偶者のみ | 1/2 | 配偶者 | 1 | 1/2 |
| 配偶者と子供2人 | 1/2 | 配偶者 | 1/2 | 1/4 |
| 子供 | 1/4ずつ | 1/8ずつ | ||
| 子供2人 | 1/2 | 子供 | 1/2ずつ | 1/4ずつ |
| 配偶者と父母 | 1/2 | 配偶者 | 2/3 | 1/3 |
| 父母 | 1/6ずつ | 1/12ずつ | ||
| 配偶者と兄弟2人 | 1/2 | 配偶者 | 3/4 | 1/2 |
| 兄弟 | 1/8ずつ | なし | ||
| 父 母 | 1/3 | 父母 | 1/2ずつ | 1/6ずつ |
| 兄弟2人 | なし | 兄弟 | 1/6ずつ | なし |
※詳しくお知りになりたい場合は、専門家にご相談ください。